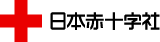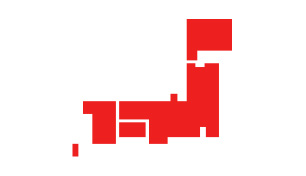| 1994年 |
日本赤十字社中央血液センター研究部にてさい帯血の採取、保存についての基礎検討の開始。 |
| 1995年4月 |
日本赤十字社医療センター産科、日本赤十字社中央血液センター研究部と検査部の協力体制でさい帯血の採取保存を開始。 |
| 1996年6月 |
愛育病院産科の採取協力開始。 |
| 1997年9月 |
「さい帯血保存についてのプロジェクト会議」発足。 |
| 1998年1月 |
「日本赤十字社中央血液センターさい帯血バンクプロジェクト」運営委員会発足。血液センター倫理委員会による調製保存方法の検討と移植手続き開始の承認。専門委員会による移植手続きの検討。 |
| 1999年9月 |
「日本赤十字社中央血液センター臍帯血バンク」へと名称変更。 |
| 1999年12月 |
採取施設として武蔵野赤十字病院と東京厚生年金病院が参加。 |
| 2001年4月 |
採取施設として三楽病院と東京衛生病院が参加。 |
| 2001年6月 |
採取施設として池下レディースチャイルドクリニックが参加。 |
| 2001年10月1日 |
都内血液センター現業部門の統合に伴い、「東京都赤十字血液センター臍帯血バンク」へと名称変更。 |
| 2005年10月 |
採取施設として葛飾赤十字産院が参加。 |
| 2006年5月 |
採取施設として池下レディースクリニック東雲が参加。 |
| 2006年12月 |
採取施設として国立国際医療センター、東峯婦人クリニックが参加。 |
| 2008年1月 |
採取施設として永寿総合病院が参加。 |
| 2010年10月 |
採取施設として昭和大学藤が丘病院、神奈川県立こども医療センター、横浜市立大学市民総合医療センター、大口東総合病院、堀病院、横浜南共済病院、済生会横浜市南部病院が参加。 |
| 2011年3月 |
神奈川さい帯血バンクの保存さい帯血、機器等の移管。 |
| 2012年4月 |
血液事業組織再編、ブロック血液センター設立、及びさい帯血バンク事業の位置づけを血液事業の関連事業とする事に伴い、「日本赤十字社関東甲信越さい帯血バンク」と名称変更。 |
| 2012年8月 |
採取施設として東北大学病院、仙台医療センター、仙台市立病院、仙台赤十字病院、東北公済病院、吉田レディースクリニックが参加。 |
| 2013年4月 |
採取施設として水口病院が参加。 |
| 2013年10月 |
採取施設として東海大学医学部附属病院、伊勢原協同病院、秦野赤十字病院、湘南藤沢徳洲会病院、海老名総合病院、やはたウィメンズクリニックが参加。 |
| 2014年1月1日 |
「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律」施行。 |
| 2014年3月 |
東海大学さい帯血バンクの保存さい帯血、機器等の移管。 |
| 2014年4月1日 |
法制化に伴い、厚生労働大臣よりさい帯血供給事業者の許可を取得。 |
| 2014年11月 |
採取施設として金子レディースクリニック、愛和病院、はやしだ産婦人科医院、山口病院が参加。 |
| 2015年8月 |
採取施設として湘南鵠沼産婦人科が参加。 |
| 2017年1月 |
採取施設として池下レディースクリニック武蔵野が参加。 |
| 2017年2月 |
採取施設として東京女子医科大学八千代医療センターが参加。 |
| 2018年2月 |
採取施設として聖路加国際病院が参加。 |
| 2019年11月 |
採取施設として関東労災病院が参加。 |
| 2022年9月 |
採取施設として桜ヶ丘病院が参加。 |
| 2024年1月 |
採取施設として東京品川病院が参加。 |
| 2024年9月 |
採取施設として共立習志野台病院が参加。 |