生命にとって血液はかけがえのないものですが、その正体や働きが知られていなかった頃には、だれもが不思議な力を持った神秘的なものと信じていました。昔、ヨーロッパでは豊作を願い血液を畑にまいたり、勇気をつけようと血液で体を洗ったり、また若返りや病気回復の妙薬として血液を飲んだりしたといわれています。

生命にとって血液はかけがえのないものですが、その正体や働きが知られていなかった頃には、だれもが不思議な力を持った神秘的なものと信じていました。昔、ヨーロッパでは豊作を願い血液を畑にまいたり、勇気をつけようと血液で体を洗ったり、また若返りや病気回復の妙薬として血液を飲んだりしたといわれています。

| 1616年 | Harvey ハーベィ 血液の体内循環論を発表 |
血液が生命や力の根源であるという考え方はとても古くからありましたが、彼の発表をきっかけに、動物の血管の中にビールや尿など、あらゆる物質を注入する実験が始まりました。
当時、注入用の器具として使われたのは、主に羽軸と動物の膀胱を組み合わせたもので、これは現在の点滴用器具の先駆けをなすものといわれています。
また、科学者のなかにさえ、子羊の血液を犬に注入すると、羊毛やひづめが生えてくるばかりでなく、そのほえ声も羊の鳴き声になってしまうと、真剣に議論した人がいたそうです。

| 1667年 | Denis ドニ 人間に対する輸血として認められている最初の輸血を行う。 |
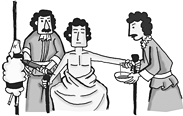
貧血と高熱のある青年に半パイント(約225mL)の小羊の血液を輸血しました。この輸血で青年は顕著な回復をみせました。この後も、彼は小羊の血液を用いて輸血を行い続けましたが、ついに一人の患者を死なせてしまいました。
このために彼は殺人者として扱われ、長い裁判の結果、無罪となりましたが、フランスでの輸血は禁止されてしまいました。これにならって、イギリス議会やローマ法王庁からも禁止令が出され、ヨーロッパでの輸血は全くなくなりました。

| 1818年 | Blundell ブランデル ガン患者に人間の血液を輸血・・・失敗 |
| 1825年 | 出産時の失血で死に瀕した婦人に輸血・・・成功 |
イギリスの産科医であったBlundell ブランデルの成功は世界中に伝わり、再び輸血についての興味を引き起こしました。
しかしながら、当時はまだ、血液型はもちろん、血液を体外に採り出したときに凝固するのを防ぐ方法も知られていなかったため、輸血に伴って起きる重い副作用や死亡事故などは当たり前のことでした。
従って、本格的な輸血の始まりは、血液型や抗凝固剤などが発見される20世紀まで待たなければなりませんでした。
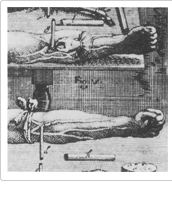 |
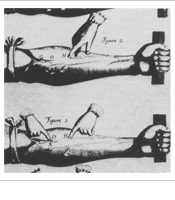 |
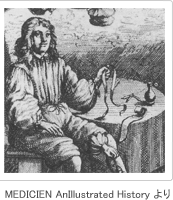 |

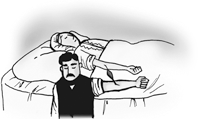
| 1900年 | Landsteiner ラントシュタイナー ABO血液型を発見 |
彼はオーストリアの医師で、人間同士の血液でも、混ぜ合わせると血球の凝集が起こる場合があることを知りました。これが今日よく知られているABO血液型の発見です。これによって、これまで輸血の際、型の合っていない血液を使用したために生じた重い副作用や死亡事故を減らすことができました。
| 1914年 | 抗凝固剤の発見 |
血液型が発見された後も、血液を体外に採り出したときに固まってしまう問題が未解決でしたが、クエン酸ナトリウムを血液に混入すると固まらないことが分かりました。
この血液型と抗凝固剤の発見により、血液を採取して保存しておき、必要なときにそれを取り出して輸血に使用することが可能になったのです。


| 1937年 | 世界初の血液銀行を設立 |
これはアメリカの医師Fantus ファンタスが、シカゴにあるCook County病院内に設立したものです。1回の採血量は500mLで、その保存期間は10日間だったそうです。
血液を血球と血しょうに分離する技術も、このころ開発されました。
また、1930年代末に始まった第2次世界大戦では、大変多くの輸血が行われ、傷病兵の生命を救いました。
| 1940年 | Landsteiner ラントシュタイナーとWiener ウィーナーがRh血液型を発見 |
| 1943年 | 血液保存液(ACD液)が開発される |
| 1944年 | Cohn コーン(米・ハーバード大学) 血しょう分画製剤の製法を完成 |


近年、輸血の方法は大きく変わりました。それまでは、まくら元輸血やガラス瓶に採取した血液をそっくりそのまま輸血する方法でしたが、今日では、プラスチック製の血液バッグに採取した血液を、血球や血しょうに分けて輸血する成分輸血が主流となっています。
また最近では、他人の血液を輸血せずに、患者さん自身の血液を輸血する自己血輸血という方法もあります。
血液が神秘的なものと信じられていた古代から今日まで、血液とその輸血は数多くの障害や紆余曲折を経てきました。そして、私たちは効果的な輸血を通して、その恩恵を受けています。こうした陰には、多くの先人たちの苦労があったことを忘れてはならないでしょう。